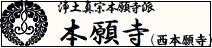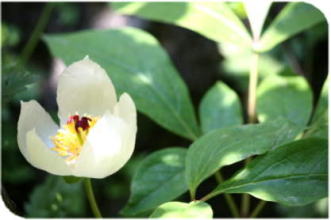f
お慈悲の用意
この前テレビを見ていましたら、中国のある少数民族の習慣で六十歳になったら自分の棺桶を作っておくというのがありました。
一昔前までは棺桶を収めて運ぶ屋根付きの、あの御神輿のような形をした箱物を家順番で管理をしていた。子供の頃はそれを見るのが怖かったという法事での思い出話。私も経験があります。
私の祖母は、「家に薪の用意が無いようでは恥ずかしいことだよ。いつどんなことがあるかわからないからのー。」と、積み上げられた割り木を見ながら話してくれたものです。
これらのそこにあるものは「人は何時かは、しかも何時死ぬかわからないのである」、という事実を実生活の中で身近に見つめていたことがわかります。
そこには、死を忌み嫌って遠ざけよう、ごまかそうという姿勢は微塵にもみられません。どのようにしても逃れられないものであることは、自然に身近な生活と一体になっていました。現代はそれを遠くにおしやって、見ぬふりをするか、見せないような偽装の中に埋没させられているような気がしてなりません。そのことがかえって悲劇を大きくしているようでなりません。用意ができないからです。
私たちは未来を試しに生きて見ると言うことは出来ません。だから毎日毎日新しい未経験の道を歩んで行くしかない、これが生きると言うことなのでしょう。そして、年を重ねるごとに、こんなはずではなかったと嘆くことがだんだんと増えてきます。人間や人生の悲劇というのは、自分の願望と現実があまりにも食い違ってくることにより、その現実を受け入れられない煩悶にあると思います。 一方に偏る価値観はもう一方の現実を受け入れることが出来ないのです。結局、対立のまま終わってしまいます。これは悲劇です。
生と死もそうです。
「みほとけに召さるるよき日近づきて誰にも言わずひとり微笑む」この短歌はある老翁の晩年の喜びの歌です。
この私は老いていくもの、病んでいくもの、死していくものという静かな諦観。そのような限りのある命を抱えているまんまの自分を決して見捨てることなく、浄土に迎えとってこの上ない仏にするという如等様のお慈悲によって対立が無くなりました。それどころか、「 死ぬ」という悲劇が「浄土に生まれる」という喜びに転ぜられているのです。 住職稿
本文へスキップ